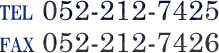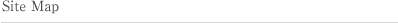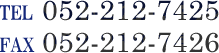| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 11月 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
コラム
36 不貞行為と離婚慰謝料(2)
2019年02月23日
先回からの続き
最高裁判所平成31年2月19日判決の事案では、「第三者Yと既婚者甲の不貞行為」と、「他方配偶者Xと既婚者甲の離婚成立」までの間に、約5年の年月が存在します。この期間に着目すれば、不貞行為と離婚の関連性は相当程度薄まっていた、とも評価できます。少なくとも、慰謝料請求をされる側としては、この点は反論したいところでしょう。
このような場合、これまでの一般的な考え方からすれば、不貞行為と離婚との間に相当な因果関係があるのか、簡単に言えば、「不貞行為ゆえにその夫婦は離婚したと言えるのか」が争点となり、この点がどのように判断されるのかによって結論は左右されたものと考えられます。なお、不貞行為と離婚の間に相当因果関係がある、という事実は、慰謝料の支払いを求める原告(他方配偶者X)側に証明責任があります。
最高裁判所平成31年2月19日判決は、他方配偶者Xから第三者Yに対する離婚についての慰謝料請求を原則として否定した上で、「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情」があるときに限って、離婚についての慰謝料を請求できると判断したわけですが、これは、これまでは「不貞行為と離婚の間の相当因果関係」を証明対象として問題にしていたものを、今後は、「特段の事情」を証明対象として問題にするよう、訴訟実務、ひいては訴訟実務を前提とする法律実務全般の変更を促す意味を持つのでしょう。
したがって、今後、この類型の紛争においては、「特段の事情」が認められるか否かが重要な問題となると容易に想像されます。
これに関し、最高裁判所平成31年2月19日判決は、「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情」と示しており、行為者の主観面に着目した「離婚させることを意図」という表現になっているわけですが、一般的に訴訟実務では、行為者の行動という客観面から行為者の内心という主観面を推認し、これを認定する、という手法が用いられることからすれば、例えば、当該第三者が、相手方が既婚者であることを知りながら不貞行為を反復するような場合には、その行為態様という外形的事情から「離婚させることを意図して」に該当するとして、「特段の事情」が認められると判断されるように思われます。
この点は、今後の裁判例の積み重ねによって明確化していくのでしょう。
また、最高裁判所平成31年2月19日判決が述べるところの「特段の事情」が認められたとしても、別途、不貞行為と離婚の間の相当因果関係は問題となると考えられます。
例えば、不貞行為終了から離婚成立までの間、長期間が経過しているような事案においては、不貞行為時において「特段の事情」は認められたとしても、不貞行為によって離婚に至ったとは言えない、と評価できるケースはあると考えられます。この二つは異なる性質のものですので、前者が認められたとしても、なお後者が否定されるケースもあるはずです。
ともあれ、今後は、この類型の紛争においては、慰謝料を請求する側に立つ場合にも、慰謝料を請求される側に立つ場合にも、最高裁判所平成31年2月19日判決との整合性を意識しなければならないでしょう。
弁護士 八木 俊行
伏見通法律事務所
名古屋市中区錦2丁目8番23号
キタムラビル401号
(地下鉄伏見駅1番出口・丸の内駅6番出口各徒歩約2分)
▷法律相談のお申し込みは