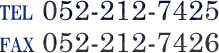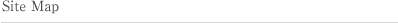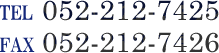| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « 11月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
コラム
58 結婚と離婚の法律問題(16) 婚姻の効力・相続分と遺留分
2019年04月16日
先回からの続き
以上に述べたところは、被相続人が遺言などで遺産の処分のあり方について何らかの定めをしていない場合における相続(法定相続)に関するものです。
被相続人は、遺言などで自分の財産(遺産)を自由に処分できます。
例えば、被相続人が、法定相続人のうちの1名に遺産全てを相続させる、という遺言を作成することもあるでしょうし、法定相続人ではない、親族ではない者に遺産全てを遺贈する、と定めることもあるでしょう。
このような場合、配偶者を含む法定相続人は、法定相続分に相当する財産を取得することはできません。
では、法定相続人は財産を一切取得できないのかと言えば、そういうわけではなく、民法上、法定相続人のうちの一定範囲の者(被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人)は、「遺留分(いりゅうぶん)」に相当する部分は取得できる、と定められています(民法1028条以下)。
遺留分制度は、一定範囲の法定相続人に、遺産のうちの一定部分を確保する制度と言えるでしょう。
簡潔に述べるならば、被相続人の配偶者の遺留分は、被相続人の遺産(相続開始時の遺産に加え、被相続人が生前にした贈与のうち一定範囲のものも加算します)から被相続人の債務を控除した部分の2分の1に相当する分に、その相続における配偶者の法定相続分(同順位の相続人がいなければ「1」となり、同順位の相続人がいるならば「2分の1~4分の3」のいずれかとなります)を乗じた分となります。
このように、婚姻の効力として、配偶者が被相続人となる相続に関しては必ず法定相続人となる点、また、遺留分権利者となる点を指摘することができます。
当然ながら、これらの効力は、相続開始時点で被相続人との間の婚姻関係が存在することを要しますから、それ以前に離婚が成立し、婚姻関係が解消されているような場合には問題となりません。
言い換えれば、婚姻関係は相続開始時点で存在すれば足り、婚姻期間の長短を問わないということですから、配偶者が、被相続人と婚姻してから短期間の内に相続が開始したような場合、他の法定相続人(被相続人の前の配偶者との間の子、あるいは被相続人の兄弟姉妹など)との間で紛争が生じる原因となることもあるでしょう。
ところで、近時、民法は、大きな改正が行われました。
まず、平成29年5月に、「民法の一部を改正する法律」が成立しました。これは民法のうち、債権法と呼ばれる分野に関する大きな改正を内容とするものであり、2020年(令和2年)4月1日から施行されることになっています。
また、これとは別に、平成30年7月に、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。これらは民法のうち、相続に関する定めを改正するものであり、2019年(令和元年)7月1日から施行されることになっています(ただし、改正法中、自筆証書遺言の方式緩和に関する規定は、すでに平成31年1月13日から施行されています)。
本コラムで述べた内容に関連するところでは、まず、遺留分に関し、遺留分権利者が権利を行使した場合の効果について、遺留分侵害額相当額の金銭の支払いを請求できることになるなどの大きな改正が行われました(なお、改正前は、遺留分権利者は、当然に金銭支払いを請求できるわけではありませんでした)。
また、被相続人の配偶者の相続に関しては、相続開始後の配偶者の居住権を保護するべく、新たな枠組みとして「配偶者居住権」、「配偶者短期居住権」が定められるなどの大きな改正が行われました(なお、改正前は、遺された配偶者の居住権に対する特別の配慮を定めた明文はありませんでした)。
これらの詳細は、機会を改めます。
続く
弁護士 八木 俊行
伏見通法律事務所
名古屋市中区錦2丁目8番23号
キタムラビル401号
(地下鉄伏見駅1番出口・丸の内駅6番出口各徒歩約2分)
▷法律相談のお申し込みは